幼児アスレチック()
たき火()
亀山ハイキング()
資料
コース別詳細図
活動時提出書類
ねらい
- 自然に親しみます。
- 思考力、判断力を育て、勇気、冒険心を養います。
- 協調性を育てます。
- 親睦をはかります。
時期・時間
- 年間を通じて活動可能です。(雨天時も可)
- 2~3時間
準備
自然の家で貸し出しできるもの
- コンパス
- 地図
- ゼッケン
- スタート幕、ゴール幕
- 無線機(代表者に1台。複数必要な場合は要相談)
- 机、イス(集計時に使用)
利用者で準備するもの
- チェックカード
- 集計用紙
- 時計、鉛筆
- 野外活動に適した服装
- 手袋
- 雨具(傘は不可)
活動内容(スコアオリエンテーリングの展開例)
留意点
- 事前に当所職員と実施方法等について打ち合わせをし、必ず現地踏査をしましょう。
- 活動中は引率指導者間の連絡を密にして、子どもたちを常に掌握し、安全と事故防止に努めましょう。
- オリエンテーリングの種類
国立曽爾青少年自然の家では、3種類のオリエンテーリングを楽しむことができます。
ポイントオリエンテーリング・・スタートから指定されたポイントを順番に回っていき、ゴールまでの時間を競うオリエンテーリングのことです。
ラインオリエンテーリング・・地図中に記入された線に沿ってコースを回り、コース上のポイント(ポイントの場所は、地図中に記されていません)を見つけていくものです。
スコアオリエンテーリング・・制限時間内に、あちこちに散在した難易度の異なるポイントを自由に(好きな順番で)回って、チェックしたポイントの合計点数を競います。学校の野外活動で最もよく行われるものです。 - コンパスの使い方を充分マスターしましょう。
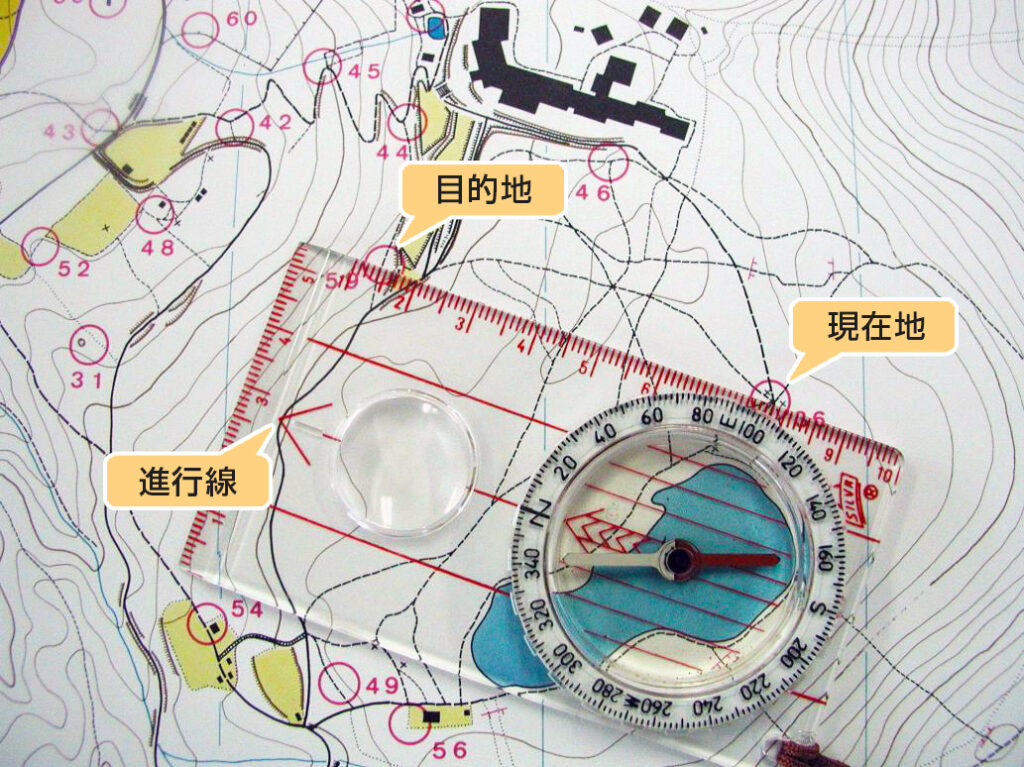
① 図上の現在地と目的地点とを結ぶ線上に、コンパスの長辺を合わせて、進行線を目的地に向けます。

②リングを回してリング内の矢印を地図の磁北線と平行にして、矢印の方位が同じになるように合わせます。
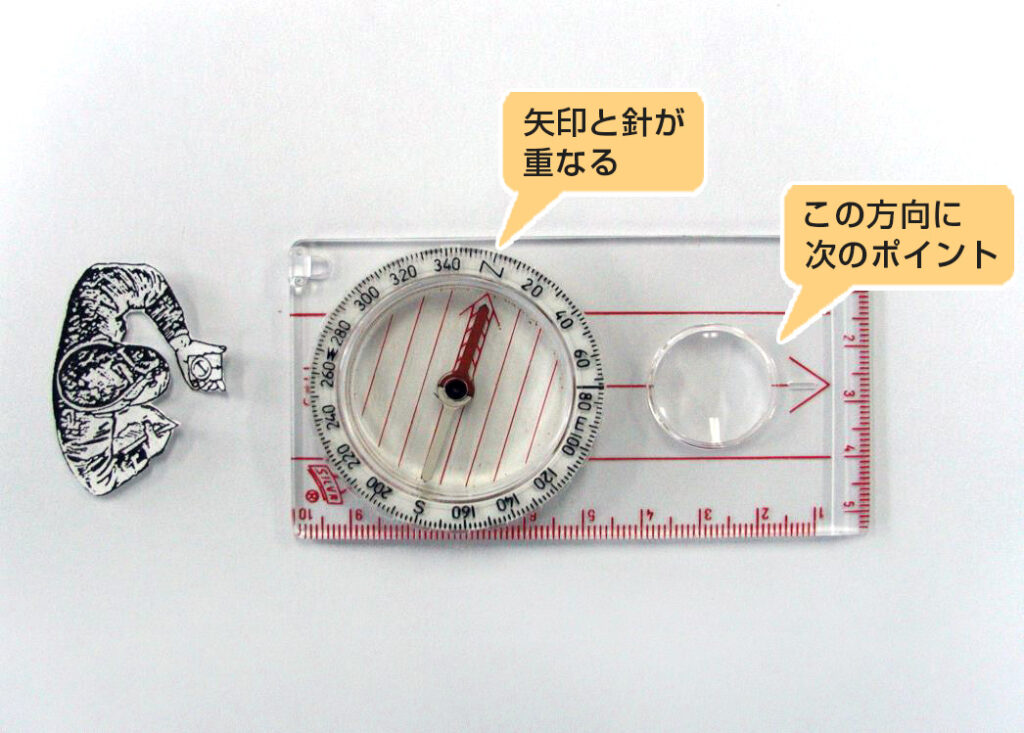
③コンパスを体の前に持ち、リング内の矢印と針(赤)が重なるまで体を回します。両方が重なった時、進行線の矢印の方向に目標物(次のポイント)があります。
このページのPDFファイル(印刷等にご利用ください)
資料
ねらい
- 見たり、聞いたり、さわったり、匂いをかいだり、味わったり、考えたりと五感を使って自然と親しみます。
- 楽しさの中に自然の不思議、おもしろさを実感的に知ることができます。
- ゲームをしながら環境への関心を高め、考える力を培います。
時期・時間
- 年間を通じて活動可能です。(雨天時も可)
- 2~3時間
準備
自然の家で貸し出しできる物
- ネイチャーサインカード★
- フライングディスク(課題で必要)
- ゼッケン
- 無線機(代表者に1台。複数必要な場合は相談要)
- バインダー(解答用紙を挟む用)
利用者で準備する物
- 解答用紙(各班に一枚を印刷しておく)
※厚紙などに貼っておくと書きやすい - ゴミ拾い用ビニール袋(グループに2枚)
- 時計、鉛筆
- 野外活動に適した服装
(長袖、長ズボン、軍手が望ましい)
★ネイチャーエクスプロアリングのサインカードは4コースあります。
- いのししコース
自然の家~お亀池~お亀茶屋~キャンプ場~なかよしホール横~自然の家 - しかコース
自然の家~なかよしホール横~キャンプ場~お亀茶屋~お亀池~自然の家
※いのししコースとしかコースは逆回りのほぼ同一コースです。
※サインカードの課題以外に、団体独自にチェックポイントを設け、課題を追加することも可能です。
活動内容
- 班編成(1グループ2人~6人程度が良いでしょう。)
- 展開例
○ネイチャーサインカードを使いながら、自然探険を楽しみます。
各グループは、ネイチャーカードの指示のもとにコースを回り、ゴールを目指します。
その間に、見たり、聞いたり、触ったり、匂いをかいだり、味わったり、考えたりと五感を使って自然を探険します。
○いくつかのポイントでは課題が出題されます。課題を解いたら解答用紙に答えを記入してください。
(指導者編)
- 指導者は、ネイチャーエクスプロアリング用具一式を準備します。
- 参加者の服装点検、健康チェックは、忘れないようにしてください。
- 参加者にネイチャーエクスプロアリングの説明をしてください。
- スタートは、3~5分程度間隔をあけスタートさせてください。(別々のコース設定も可)
- 指導者は、巡回を行い安全にゲームが進行されているかを確認してください。
(参加者編)
- ネイチャーサインカード上側の矢印、真ん中の写真、写真の下のアイコン、文章を読み次にどこへ行くか、何を見つけに行くのかを判断してください。
- 競争ではありません。班長を中心に協力し、全員そろってゴールしてください。
(ネイチャーサインカードの見方)
- 矢印は、写真で示されているポイントが見えるか、見えないかがわかります。それぞれの矢印を参考にしてください。
- 写真は、次にめざすポイントや探すものが示されています。(目的のものばかりに気をとられず、写真の中のヒントとなるもの(看板、道や周りの景色等)にも注目してください。)
- アイコンは、写真で示されているポイントで何をするかを示すマークです。
- 詳しいことは、ネイチャーサインカードに記入されてあります。
- いくつかのポイントでは、課題が出されています。課題を解いたら解答用紙に答えを記入して次に移動してください。
- 課題の得点合計で順位が決まりますが、順位はあくまでも最後の小さな楽しみです。ゆっくり自然を感じることを楽しんでください。
留意点
- 自然を大切にしてください。(木を折ったり、花をきずつけたりしないようにしてください。)
- 道路横断時など車に気をつけ、交通ルールをよく守って行ってください。
- 自然を感じとることを大切にして行ってください。早さを競うものではありません。
このページのPDFファイル(印刷等にご利用ください)
資料
フォトテーリング (2025.4~ 新しくなりました。)()
資料
ディスクゴルフ()
資料
当所のフィールド・アスレチックは、コナラ、ミズナラ等の木立の中に、自然の地形を利用して、約300mのコースに意図的に木材やロープを用いて13種目のポイントを配置しています。子どもたちが、それらに挑戦することによって気力や体力を養うとともに、内在する冒険心を子どもたちが、それらに挑戦することによって気力や体力を養うとともに、内在する冒険心をも満たすべく設けられたものです。
ね ら い
(1)困難な種目に直面しても、勇敢に対処する強い意志を養うことができます。
(2)グループで励まし合い、助け合いながら進んでいくことによって、協力の大切さを知らせることができます。
(3)各ポイントで体全体を使うことにより、体力の向上をめざします。
(4)木立の中で体を動かす喜びを味わいます。
時期・時間
(1)年間を通じて活動可能
(2)1時間30分~2時間
準 備
| 自然の家で貸し出しできる物 | 利用者で準備する物 |
| 無線機(代表者に1台。複数必要な場合は相談要) | 野外活動に適した服装 手袋 |
留 意 点
(1)山の斜面に沿って設営しているため、天候等により、全部または一部の使用を禁止する場合があります。
(2)引率指導者は、事前にコースの下見をしておいてください。その際、危険箇所や利用者個々の能力により、
各ポイントが実施できるか否かを判断していただくとともに、引率指導者の配置が必要な場所の確認を
お願いします。
※雨の後はすべりやすいので、必ず引率者が確認してからスタートしてください。
(3)引率指導者は、フィールド・アスレチックの種目紹介や安全確保及びその他必要事項について、事前に参加者に
説明しておいてください。
(4)本アスレチックは、引率指導者の直接指導のもとに行ってください。
(5)けが等の事故、天候の急変など緊急を要する場合の連絡及び処置の方法について、事前研修をお願いします。
(無線機をお渡ししますので、必ず携帯し、緊急の場合は当所事務室と連絡をとってください。)
種目紹介
| 番号 | 種 目 | 内 容 | 注意事項 |
| 1 | 丸太ころがし | グループで助け合いながら体や棒で丸太を転がし、往復する。 | 左右均等に力を加える。 丸太に手や足を巻き込まれないように注意する。 |
| 2 | 長ゲタすすみ | グループで助け合いながら長ゲタの上に乗り、呼吸を合わせて進む。 | 他のグループのペースを気にせず、自己のグループのペースを守る。 リーダーが号令をかけてから始めると進みやすい。 |
| 3 | トンボうつり | 一人でブラブラする丸太の上を進む。 | ロープをしっかり持って進む。 滑るので注意する。 |
| 4 | つり橋わたり | 一人で丸太に登り、ブラブラするつり橋を渡る。 | 一人ずつゆっくり渡ること。 雨の後等は滑りやすい。 後続者はロープを揺らさない。谷を渡るため転落に注意。 ※引率者の配置が必要。 |
| 5 | 曽爾高原飛行 | 一人でロープにつかまって空中を滑り降りる。 | ロープをしっかり持つこと。 着地に注意する。 後続者はロープを揺らさない。 谷を渡るため転落に注意。 ※引率者の配置が必要。 |
| 6 | 岩壁のぼり | 一人で丸太をよじのぼって進む。 | 滑りやすいのでしっかり持って登ること。 グループで助け合っても良い。 |
| 7 | ネットとびつき | 一人でロープにぶら下がりネットに飛び移る。 | ロープをしっかり持ち、ネットにとびつく。 握力の弱い人はロープを股に挟むと良い。 |
| 8 | 円盤飛行 | 一人で円盤に乗り、ロープを引っ張って進む。 | バランスを崩さないこと。 着地に注意する。 |
| 9 | 洞窟探検 | 一人で丸太の穴をくぐりぬけて進む。 | 頭の方から進み、頭を打たないように注意する。 丸太の上を歩くのも良い。 |
| 10 | 一本綱わたり | グループの仲間が引っ張っているロープの上を一人で進む。 | ロープをゆるめたり揺らしたりしないこと。 上部のロープをしっかり持っていること。 雨の後等は滑りやすい。 |
| 11 | 冒険とりで | 丸太やロープを一人で工夫しながら渡る。 | 一人ずつ渡ること。 後続者は揺らさないこと。 雨の後等は滑りやすい。 |
| 12 | お城ジャングル | 丸太やロープをつたわって展望台に登る。 | 降りる時に注意する。 雨の後等は滑りやすい。 |
| 13 | 丸太つきあげ | グループで、1、2の3の合図で丸太を引き上げ、球を3回突く。 | 丸太が落ちる時に注意する。 |



このページのPDFファイル(印刷等にご利用ください)
資料
川遊び()
注)川遊びは指導が必要なプログラムです。(資料を更新しました令和7年7月)
活動時提出書類
資料
実施当日、スライド等を用います。



